この記事を読むとわかること
- 『光が死んだ夏』の舞台モデル候補地
- 各シーンと現地風景の共通点
- 御杖村や名張川などのロケ地的魅力
- 作品が表現する“田舎の空気感”の再現性
2025年夏アニメ『光が死んだ夏』の舞台・クビタチ村は、静かな田舎の山間集落として描かれ、そのモデルとなった可能性の高いロケ地に注目が集まっています。
公式情報はまだ明らかにされていませんが、三重南部〜奈良県御杖村周辺がその候補地としてSNSやファンサイトで話題に。
この記事では、作中に登場する風景や舞台設定をもとに、聖地巡礼におすすめのモデル地やその魅力を詳しく解説します。
モデルは三重南部の山間集落?
『光が死んだ夏』の舞台・クビタチ村は、山に囲まれた静かな田舎の集落として描かれています。
そのモデル地として最も有力視されているのが、三重県南部〜奈良県境に位置する御杖村(みつえむら)です。
作中では、三重弁の会話や「伊勢志摩ナンバー」の車が描かれており、地理的にも三重県内である可能性が高いとされています。
御杖村は自然豊かで、山林や川沿いの風景、古い道標などが点在しており、作品の雰囲気と非常に一致するロケーションです。
また、作者・モクモクれん氏は「自分の育った田舎をモチーフにした」と発言しており、三重県出身であることもファンの間で知られています。
このことからも、地元に近いエリアが舞台のベースになっている可能性は高いと考えられます。
聖地①:度会町・白山高等学校が校舎モデル?
アニメに登場する希望ヶ山高校の外観は、三重県度会町に実在する「白山高等学校」がモデルとされています。
SNSでは、「校門の形状」「校舎の配置」「背景の山並み」などが似ていると話題になり、ファンの間で“聖地”として注目を集めています。
実際に訪れたファンが比較画像を投稿するなど、聖地巡礼先としての人気も高まりつつあります。
白山高校は、現在も現役の高校であるため、見学する際には節度を持った行動が求められます。
作品の背景画では、建物だけでなく“空の広さ”や“背後の山の奥行き”など、土地特有の雰囲気が丁寧に再現されています。
学校シーンは『光が死んだ夏』の中でも象徴的な場面が多く、実際の風景と照らし合わせて見ると、より深く作品世界を感じられるでしょう。
聖地②:御杖村の首切地蔵と山久商店
作中に登場する“首切地蔵”という名称は、実在する「首切地蔵(くびきりじぞう)」と一致しており、三重県と奈良県の県境・御杖村にある地蔵尊がモデルではないかと指摘されています。
この地蔵には古くからの伝承があり、首をはねられた怨霊を鎮めたという由来を持つ、地域でも有名なスポットです。
アニメでは、この地蔵の前で不穏な雰囲気のカットが使用されており、“何かが起こる場所”の象徴として登場しています。
また、作中に描かれる商店「山久(やまきゅう)」も、御杖村に実在する「阪口商店」がモデルと考えられています。
建物の形や看板の雰囲気がそっくりで、地元の人々にとっても親しみのある店が作品に反映されているのが興味深いところです。
どちらのスポットも、“現実に存在するけれど、どこか異世界のような感覚”を味わえるロケーションとなっています。
聖地③:川沿いの橋や林道/名張川沿いの道
第1話をはじめ、アニメ『光が死んだ夏』には川沿いの橋や林道の風景が数多く登場します。
特に、ヒカルが帰ってきた場面で使われた橋の構図は、三重県名張市を流れる名張川沿いの景観に非常に似ていると話題です。
山間を縫うように走る小道や、苔むしたガードレール、鬱蒼とした林道など、実在する風景との一致度が高く、臨場感を引き立てています。
また、作中では音が消えるような無音演出と共に、川のせせらぎや虫の声が強調されており、“静けさの中の異物感”を感じさせる描写が際立ちます。
この“橋”や“林道”の演出は、物語の核心となるシーンの背景として繰り返し使われるため、聖地巡礼の中でも印象深い場所となり得るでしょう。
作品のもつ不穏さや喪失感が、このリアルな風景によってより一層強調されているのです。
完コピではないが“空気”はそのまま
『光が死んだ夏』の背景美術は、現実の風景を忠実に再現しているわけではありません。
しかし、その代わりに、“空気感”や“匂いまで想像できるような静けさ”を丁寧に描いています。
作者・モクモクれん氏は、インタビューなどで「自分が育った田舎の感覚を重視して描いている」と語っており、個人的な記憶が背景に込められていることがわかります。
そのため、完全なロケ地として一致する場所は少ないかもしれませんが、御杖村周辺の風景は非常に近い感触を持っています。
風の音、虫の声、夕暮れ時の影の長さ――それらが織りなす演出が、作品世界をリアルに感じさせてくれるのです。
聖地巡礼というと「完全一致」の探訪になりがちですが、本作では“雰囲気を味わう旅”が最適と言えるでしょう。
まとめ|静寂の中の異物感を巡る旅へ
『光が死んだ夏』は、特定の実在の場所を完全に再現した作品ではないものの、三重県南部や奈良・御杖村周辺の風景が随所に反映されています。
山間の集落、静かな川沿いの道、どこか古びた商店や地蔵――。
それらはすべて、“日常に潜む異常”という物語のテーマにぴったりと重なります。
モデル地を巡ることで、作品の中に漂う空気や違和感を、五感で体験することができます。
聖地巡礼の醍醐味は、単なる一致を探すことではなく、作品の“気配”を感じることにあるのです。
もしあなたが作品の世界に深く入り込みたいなら、この静寂と違和感の土地を、実際に歩いてみる価値があるでしょう。
この記事のまとめ
- 舞台モデルは三重・御杖村周辺が有力
- 白山高校や首切地蔵が聖地候補として話題
- 名張川沿いや林道など風景との一致点が多い
- 実在の場所をベースに“空気感”を描写
- 聖地巡礼では一致よりも雰囲気を楽しむのが醍醐味

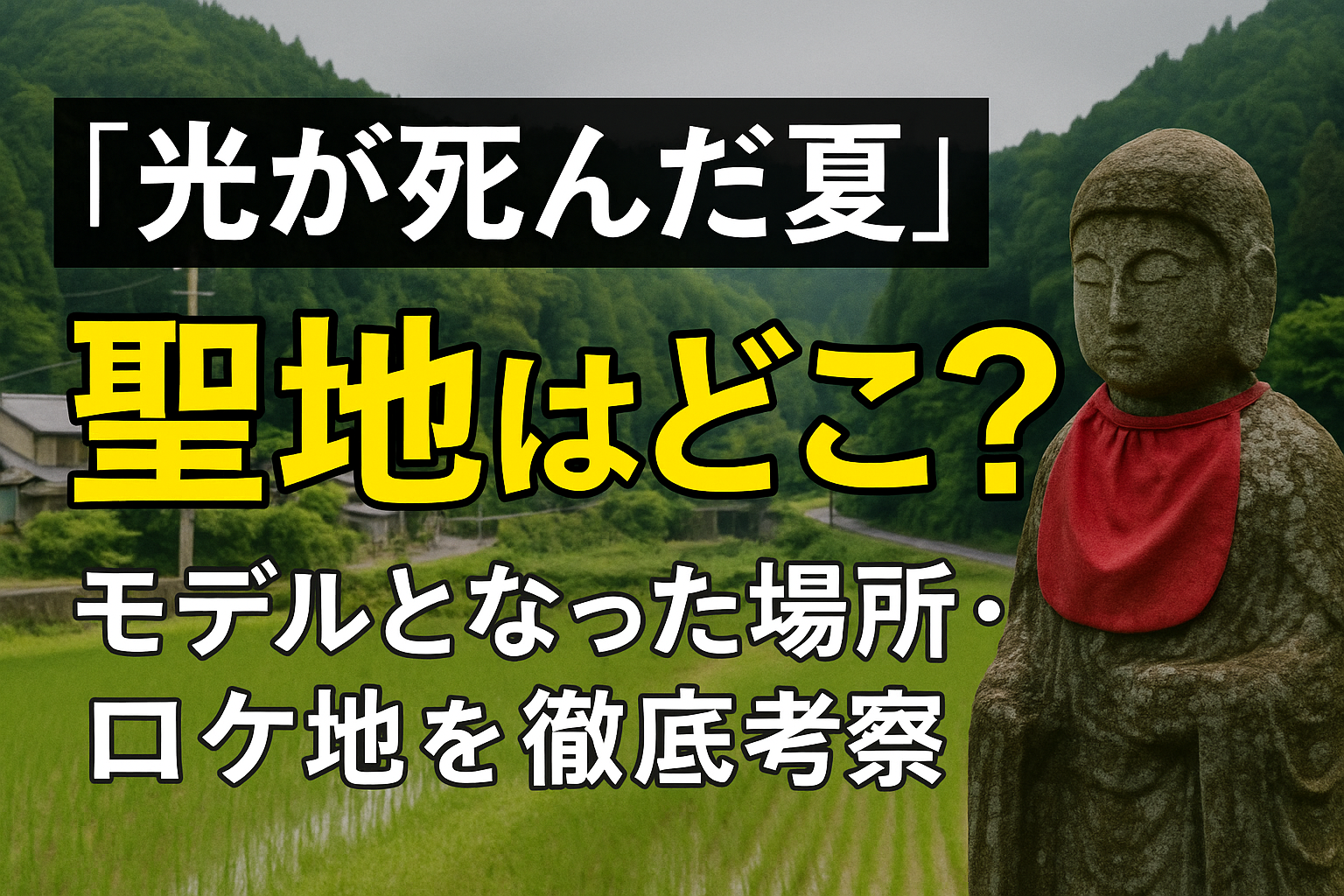
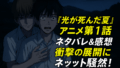
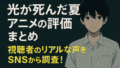
コメント